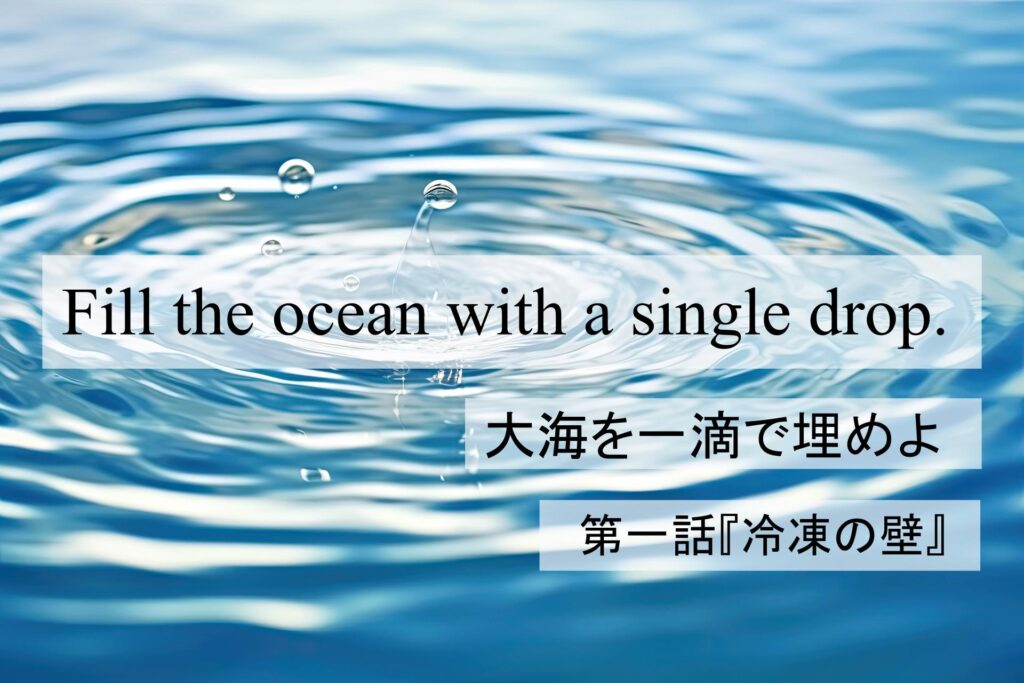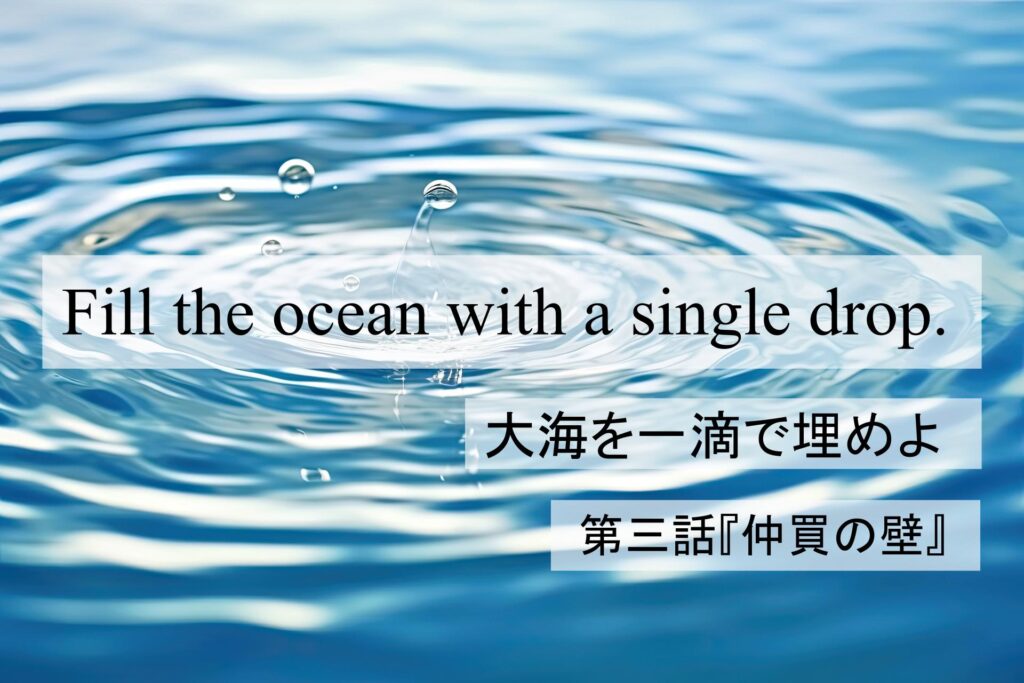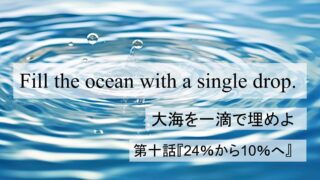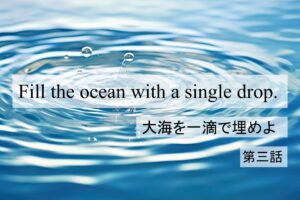Fill the Ocean with a Single Drop『大海を一滴で埋めよ』第二話:「鮮魚の壁」
第二話:「鮮魚の壁」
このドラマは、対馬水産による新規プロジェクトをユーモアとリアリティを交えて描くノンフィクション・シリーズです。
敗因を分析し、冷凍サンプル配布から「解凍後サンプル」配布へと戦術を転換。
2025年3月31日【大阪・対馬水産 営業本部 会議室】

【参加者】
大阪 営業所:塚口、児島、長谷川
-曇り空
壁には全国の水産統計グラフと対馬の地図。
PC画面には売上推移や出荷数のグラフが映し出され、
会議室には、重く張り詰めた空気が漂っている。
(扉が開き、長谷川と児島が入室。足取りは重い)
塚口部長(椅子にもたれ、天井を見上げたまま)
「……で?
豊洲は、どうだった。」
児島(資料を差し出しながら)
「すみません……今回も、発注には至りませんでした。
話は聞いてもらえましたが、結果はゼロです。」
塚口部長(鼻で笑い、ゆっくりと目線を戻す)
「……だから言っただろう。
冷凍魚は、所詮“冷凍魚”だって。
「高級漁法」「凍眠処理」って、こっちがどれだけ語っても、
それは結局、我々の“事情”に過ぎない。」
(資料を静かに机に置く)
「売りたい価格と、買いたい価格は、根本的に違う。
冷凍魚は、冷凍魚としての流通でしか売れない。
それが――現実だ。」
(沈黙。その空気を、若い声が切り裂く)
長谷川(22歳・女性。熱く、まっすぐな瞳で)
『……でも、それじゃあ、漁師さんたちはどうすればいいんですか!?
もう、昔みたいには獲れないんです。
気候も、海流も変わって、漁獲量はどんどん減ってる。
それでも、みんな毎日、海に出ています。
せっかく質のいい魚を獲っても、「冷凍だから安く」なんて――
そんなの、悔しすぎます!』
(少し息を整え、トーンを落とす)
「ちゃんとした価値で、ちゃんと届けたいんです。
そうでなければ、漁業も、加工業も……続けていけません。」
児島(55歳。静かで、重い声)
「……それは、俺たちも同じだ。
理想と現実は分けろって、何度も言ってきた。
でもな――」
(長谷川を見て)
長谷川
『もし、『冷凍なのに冷凍じゃない』と言える魚があったら?
解凍してもなお、鮮魚より鮮度が高い魚があれば――
私達にも、勝負の場があるかもしれない。』
塚口部長(やや呆れたように、苦笑)
「……本気で言ってるのか、長谷川?
誰がそんな話、信じるんだ?
『冷凍なのに冷凍じゃない』
『鮮魚より鮮度が高い冷凍魚』――
そんな言葉、この業界には通じないよ。」
長谷川(一歩前に出て)
『今日、大川部長にお礼の電話を入れたとき、先日の穴子サンプルの話になりました。
「白焼きで食べたら、とても美味しかった」と――お褒めの言葉をいただきました。
食べてもらえさえすれば、この価値は必ず伝わると、私は信じています。』
塚口部長(資料を見ながら、眉をひそめる)
「……ジャパンクオリティ、か。
ブランド魚、活け締め、真空パック、凍眠処理――そこにチルド便での空輸。
理屈は通っている。
だが……価格が重すぎる。
冷凍魚としては、あまりにも高い。」
(静かに笑いながら)
「私はどうしても納得できない。
冷凍を解凍して、鮮魚と同じ価格で売れるとは思えない。
だったら、空輸なんてやめて、船便で安く出せばいい。
現地で都合よく解凍すれば、鮮度もロスも、コントロールできる。
それが一番、合理的だろう?」
長谷川(強く、前に出る)
『確かに、合理的です。そして、その市場も否定しません。
でも――その流通では、数をさばく事ができません。
どうしても冷凍の壁、「冷凍魚の価格競争」に巻き込まれてしまいます。
私たちが目指すのは、そこじゃない。
もう今は薄利多売できない
“価値”で勝負する流通――
鮮魚便に乗ること。
それが、対馬の魚を未来につなぐ道だと、私は信じています!』
児島(静かに)
「問題は、その「鮮魚便」という商流に、
どうやって乗せていくか――だな。」
長谷川(まっすぐに)
『「鮮魚便」という、大きな市場の“ニッチ”を狙う。
一滴の魚が、大海を変える。
私は、そう信じています。』
児島(目を閉じて、うなずく)
「……今度は、“鮮魚の壁”、か。」