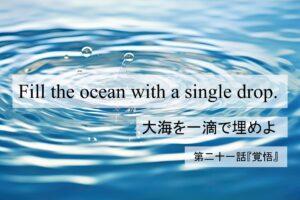底引き網漁─大型化とその背景
対馬近海では近年、大型船による底引き網漁が急速に増加しています。
その背後には、漁業構造の変化、国際的な競争、そして補助制度の存在といった複合的な要因があります。
この記事では、その主な理由や与える影響をご紹介いたします。
底引き網漁が拡大する6つの理由
日本の漁業現場で底引き網漁が再び拡大しているのは、単に効率を追求するためだけではありません。人手不足や燃料費の高騰、魚種の変動といった漁業を取り巻く環境の変化が、漁法の選択に強く影響しています。
以下では、そうした背景の中でなぜ底引き網漁が選ばれているのか、その理由を6つの観点から掘り下げていきます。
1. 底引き網漁の近代化と大型漁船の導入

日本の漁業では、1970年代以降、漁船の大型化と操業の近代化が進展しました。
とくに底引き網漁においては、60トン級から100トンを超える大型船の導入が進み、長距離・長時間の操業が可能となりました。
冷凍設備や自動巻上げ機器、GPS・魚群探知機などの機器が搭載されることで、少人数でも高い操業効率が得られるようになり、
収益性を重視する現場では、大型船による底引き網漁が拡大していきました。
2. 豊かな漁場で広がる底引き網漁の活用

対馬近海は、暖流(対馬暖流)と冷水系の潮流が交差する海域に位置し、プランクトンの発生も多いため、古くから多様な魚種が集まる日本有数の豊かな漁場として知られています。
この海域では、季節や年ごとに漁獲される魚種が大きく変わるため、漁業者にとっては高い柔軟性と対応力が求められます。
近年では、このような環境において漁業の安定性を確保するための手段の一つとして、底引き網漁の導入が進みつつあります。
3. 資源変動に対応する底引き網漁の役割

対馬近海では近年、漁業資源の構成に大きな変化が生じています。
従来、底引き網漁の主要対象だったタラやエビ類などの資源が減少傾向にある一方で、スルメイカやサバ、アジなど回遊性の強い魚種が新たな漁獲対象として台頭しています。
こうした魚種の変動や不安定さに対応するため、対象を限定せず広範囲を一網で捕獲できる底引き網漁の利用が拡大しています。
魚種ごとに漁法を使い分ける手間を省きつつ、一定の収益を見込める点が、漁業者にとっての選択の背景にあると考えられます。
ただし、魚種を選ばないという特性は、未成魚や非対象魚の混獲リスクも高く、資源管理の観点からは慎重な運用が求められます。
4. 外国漁船との競合と底引き網漁の強化

対馬海域は東シナ海に面しており、韓国や中国などの外国漁船との操業エリアの重複が問題となっています。
これらの国では、大型の底引き網漁船が多数投入されており、漁場の競合が年々激化しています。
こうした国際的な競争のなかで、日本の漁業者も操業効率を高める必要性に迫られ、底引き網漁の近代化や大規模化が進む一因となっています。
5. 沿岸漁業の衰退と底引き網漁への転換

日本各地の漁村では、かつて主流だった沿岸漁業が急速に衰退しています。
漁業者の高齢化や後継者不足、燃料費や修繕費などのコスト増加により、小型船による近距離の漁では採算が合わず、漁業そのものから撤退するケースも増えています。
こうした構造的な困難に直面する中で、省力化・効率化が可能な底引き網漁へと転換する動きが一部で進んでいます。
特に、大型船と自動化機器を組み合わせることで、少人数でも広範囲を漁獲できる底引き網漁が、厳しい経営環境の打開策として選ばれる傾向があります。
6.補助制度が後押しする底引き網漁の拡大

底引き網漁の拡大には、漁業構造の変化やコスト面での合理性に加えて、公的な補助制度の影響も大きく関わっています。
日本の漁業政策では、漁船の大型化や漁具の近代化、省力化設備の導入などに対して、国や自治体からの支援が幅広く行われています。
こうした制度は、漁業の効率化や担い手の負担軽減を目的としたものであり、現場で一定の成果を上げてきた一方で、環境負荷の高い漁法にも資金が流れやすい構造を生んでいる側面があります。
その結果、底引き網漁の導入や継続が経済的に後押しされるかたちとなり、現場の選択を左右する要因のひとつとなっています。
短期的な収益確保に資する制度であっても、水産資源や海底環境への影響とどう両立させるかが問われており、補助制度の設計そのものにも、持続可能性の視点が求められています。
底引き網漁が海底環境と水産資源に及ぼす影響

底引き網漁は、海底に網を接触させながら広範囲を曳いて漁獲する漁法です。
一度に多種多様な魚介類を獲ることができるという利点がある一方で、海底の砂泥や藻場を物理的にかき回してしまうという特徴があります。
こうした影響により、稚魚や底生生物が巻き込まれて捕獲されたり、産卵場が破壊されたりする可能性があることが、各地の調査や研究で指摘されています。
特に、同じ海域で繰り返し操業が行われる場合、底生生物群集の多様性が失われることや、資源の再生産能力が低下するリスクが懸念されています。
日本のように多様な生態系が存在する沿岸海域においては、底引き網漁が生態系サービスに与える影響を適切に評価し、資源の維持と漁業の継続を両立させる取り組みが求められています。
まとめ──海を壊さず、未来につなぐための選択
対馬水産は、こうした現実に向き合い、海を壊さない漁法を行う漁師との直接提携を選びました。
底引き網を使わず、資源の豊富な「旬の大漁日」に限定して活魚を買い付け、現場で活けジメ・真空パック・急速冷凍。
鮮度を封じ込めたまま、長期保存が可能な高品質な冷凍魚に仕上げています。
これにより、賞味期限が長く、廃棄ロスの少ない、環境と共生する水産物流通のかたちを実現しています。
私たちは、対馬の海でしかできない方法で、持続可能な漁業の未来をつくり続けます。

--320x180.jpg)
-さむね-320x180.jpg)