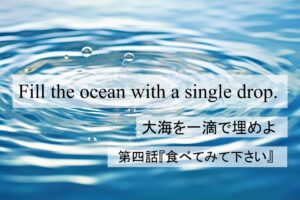日本の漁業が直面する課題とその解決策
日本の漁業は今、かつてないほど深刻な課題に直面している。かつて世界有数の漁獲量を誇ったこの国の漁業は、地球温暖化や乱獲に加え、産業構造の変化や経済的な困難にも見舞われている。
1.日本の漁業が抱える課題とは?
日本の漁業を取り巻く環境は大きく変化しており、資源、担い手、経済性、そして養殖業において深刻な問題が顕在化している。
魚資源の減少と気候変動の影響

水産庁によると、日本の漁獲量は1984年のピーク時(約1,282万トン)から2022年には約364万トンにまで激減した。
乱獲や海水温の上昇によって、サンマやイカといった回遊魚の漁獲が困難になり、漁業の不安定化が進んでいる。
また、国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストでは、ニホンウナギやクロマグロなどが絶滅危惧種に指定されており、資源管理の強化が喫緊の課題となっている。
漁業者の高齢化と後継者不足

2020年時点で漁業就業者は約13万人、そのうち65歳以上が約40%を占めるなど、高齢化が深刻である。
1993年には約41万人いた漁業従事者が、現在は3分の1以下に減少し、漁法や地域の知恵を継承する若手の確保が難しくなっている。
経済的負担の増加(燃料費・餌代の高騰)

漁業を支えるコストも上昇している。燃料費や餌代などの経費が年々高騰し、漁に出るたびに赤字となるケースも見られる。
これにより、「漁に出ても儲からない」構造が定着し、離職や新規参入の障壁が高まっている。
養殖業の課題と限界

天然魚の減少を補うために養殖業が注目されているが、高コストや稚魚の低生存率、飼料となる小魚の乱獲といった課題もある。
完全養殖が難しい魚種では、いまだに天然の稚魚を採取する方法が主流であり、これも資源の枯渇につながりかねない。
これらの課題に対し、日本の漁業が進むべき道として、以下のような取り組みが重要である。
2.日本の漁業を再生するための解決策とは?
これらの課題を乗り越え、日本の漁業を持続可能な産業へと再生させるために、次のような取り組みが必要である。
資源管理型漁業の推進

科学的な資源評価に基づいた漁獲管理や漁期の制限などを導入し、回復を前提とした持続可能な漁業制度を構築することが不可欠である。
養殖技術の高度化と効率化

完全養殖技術の研究開発を進め、生産効率の向上と環境負荷の軽減、コスト削減を同時に実現していく必要がある。
若手漁業者の育成と支援

労働環境の改善、収益性の向上、就業支援制度の拡充により、若者が希望を持って参入できる環境づくりを推進する。
コスト構造の見直しと補助制度の整備

高騰する燃料費や餌代に対する支援策、流通改革を通じて、採算のとれる漁業経営を目指す。
3.「薄利多売」から「高品質・高付加価値」へ

限られた魚資源、そして高騰する原料魚を背景に、もはや安売り大量販売の時代ではない。
今後は鮮度と品質を重視した高付加価値商品を軸に、適正な価格で販売できる販路の確保が重要である。
また、国内市場の縮小を見据え、海外の和食店や高級食材市場への輸出を積極的に展開し、ブランド力を高めていくことが求められる。
未来の食と海を守るために、日本の漁業は「量」ではなく「質」を重視した新たな価値創造と、グローバルな視野を持った挑戦が必要とされている。





--320x180.jpg)
-さむね-320x180.jpg)